
カトリック大江教会
住所:〒863-2801 熊本県天草市天草町大江1782電話:0969-42-1111
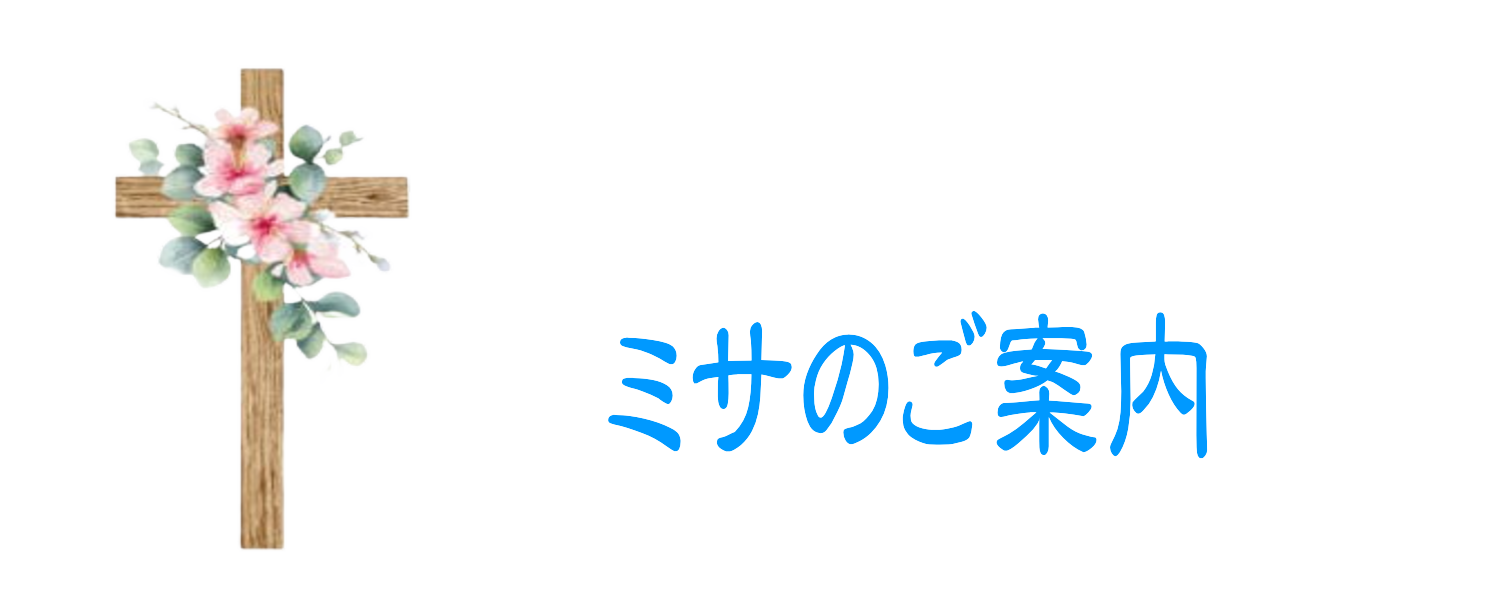
◆主日ミサ
毎週 土曜日 午後6時30分から
◆平日ミサ
井手神父さまの都合で曜日や時間が変更になることがあります。今後のミサ予定を確認してからおいで下さい。
◆今後のミサ予定
○1月17日土曜日 夕方6時30分から 年間第2主日 入門講座
○1月24日土曜日 夕方6時30分から 年間第3主日
2026年1月
見よ、新しいことをわたしは行う。今や、それは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。わたしは荒れ野に道を敷き砂漠に大河を流れさせる。
イザヤ書43章19節 新共同訳聖書
2025年12月
主の律法は完全で、魂を生き返らせ主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。主の命令はまっすぐで、心に喜びを与え主の戒めは清らかで、目に光を与える。主への畏れは清く、いつまでも続き主の裁きはまことで、ことごとく正しい。金にまさり、多くの純金にまさって望ましく蜜よりも、蜂の巣の滴りよりも甘い。
詩編19編8節から11節 新共同訳聖書
2025年11月
そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、 忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。 希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。
ローマ書5章3節~5節 新共同訳聖書
2025年10月
主は命を絶ち、また命を与え
陰府に下し、また引き上げてくださる。
主は貧しくし、また富ませ
低くし、また高めてくださる。
弱い者を塵の中から立ち上がらせ
貧しい者を芥の中から高く上げ
高貴な者と共に座に着かせ
栄光の座を嗣業としてお与えになる
サムエル記上2章6節から8節 新共同訳聖書
今年も美しいイルミネーションが完成しました。


2025年9月27日土曜日
熊本地区教会合同巡礼ミサ
熊本地区宣教司牧評議会主催の巡礼ミサが、大江教会で捧げられました。


熊本地区所属の15教会から満遍なく信徒さんたちが集い、アベイヤ司教さまの司式のもと、司祭団と信徒200余名が揃いました。これだけの信仰者たちが一堂に会して私たちの主イエス・キリストを賛美するというのは実に荘厳であり、たましいが揺さぶられるような感動に満たされました。
天の御国ではきっと、時間の制限なく、こんな賛美がずっと続いているのだろうな、と想像すると、なんとも夢心地になり、幸せホルモンが溢れてきました。

ミサのひとときは、現実世界の労苦を忘れ、空洞の、乾ききった肉体に、そして霊とたましいにしっかりとちからをいただける時間です。少なくとも私はそうですし、会堂に集われた全ての信徒さんが同じ思いでありますようにと祈りました。
今年は通常聖年にあたりますので、特別な免償を受けるために、たくさんの信徒さんたちが罪の告白とゆるしの秘蹟をうけました。
アベイヤ司教さまの説教は、「希望は欺かない」という内容でした。

その基本は、くしくも殉教者アダム荒川の言葉でした。
朽ち果てるものではなく、また、寿命が尽きるとだれも等しく死んでいく人間にでもなく、ただ神に、イエス・キリストにのみ、望みを託して信仰の旅路を歩いて行く。
そうですね。マタイの福音書24章35節に「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない」。と書いてあります。マルコ13章31節にも同じ事が書いてありますし、イザヤ書40章8節には「草は枯れ、花はしぼむがわたしたちの神の言葉はとこしえに立つ」とあります。
言葉は神であり、神はイエス・キリストです。ただ神に、イエス・キリストにのみ、望みを託して信仰の旅路を歩いて行く巡礼者。それが私たちである。
アダム荒川のように、強く雄々しくあれ。
アベイヤ司教さまはそんな内容で説教を締めくくって下さいました。
またいつか、どこかの教会に集い、旧交をあたためあい、そしてともに主イエス・キリストを賛美する機会を与えて下さるように、信徒皆さんが祈り願った一日でした。
2025年9月8日月曜日
イタリア巡礼団ミサ
イタリアから大司教さま、神父さま方、信徒の皆さん計25名が来島され、ミサが捧げられました。
天草の教会ばかりではなく、熊本の手取教会・島崎教会・帯山教会・健軍教会などからも信徒さんが集まりました。
イタリア語の歌や説教は全く解りませんでしたが、ラテン語の聖歌をともに歌い、日本語の聖歌も数曲あって、こころをひとつにしてイエスさまの救いと贖い、そして愛をかみしめる特別な時間を共有出来たことはなににも代えがたいひとときでした。
イタリアの皆さんも日本の信徒さんたちも、最後はポロポロと涙を流しながら「希望の巡礼者」を歌いました。
世界どこへいっても同じ歌を歌い、同じミサに与ることができる。カトリックに所属していることの幸いを改めて感謝致しました。



2025年8月20日水曜日
川口敏神父さま 特別ミサ
天草市大江出身の川口神父さまが、「聖心のウルスラ宣教女修道会」所属シスター方と来島して下さり、特別ミサを司式して下さいました。
簡潔で解りやすい説教に聞き入りました。
ぶどう園の仕事に従事した労働者たち。朝早くから働いた人たちも、半日働いた人たちも、そして、終業時間ギリギリにぶどう園に入ったひとたちも、皆同じ賃金でした。
当然、早くから働いた人たちは「不公平だ!」と文句を言います。でも、ぶどう園のオーナーは言うのです。「わたしは皆に同じだけ報酬を上げたいのだ」と。
真面目な(?)私は、誰よりも早くに畑に行き、誰よりも遅くまで仕事をするだろうと思います。そして、短気ですから、オーナーに食ってかかり、ほとんど仕事をせずに1日分の賃金をせしめたずるいひとたちに嫌みタラタラ言うだろうな、と思って神父さまの説教を聴いていました。
でも、神さまはそんなクレームなどおかまいなしに仰るのです。「わたしはそうしてやりたいのだ」と。
川口神父さまも、ご自身の経験から「ああ、なんと神さまは太っ腹だろう。神さまの救いと愛はなんと素晴らしいのだろう」としみじみと思い知らされた。そんなお話をして下さいました。
私がオーナーだったら・・・、(悪い意味で)決してこの聖書のようには行動しないだろうと思います。
そうやって、自分を省み、そこから再度、神さま・イエスさまの愛と憐れみを黙想出来た今日の御ミサは、なによりの財産になりました。
ミサには、長崎の「お告げのマリア修道会」から巡礼に来られたシスター方もご一緒でした。大江教会からシスターの姿が消えて以降、久しぶりの光景でした。
あたたかい主の愛に包まれたひととき、川口神父さまとシスター方にこころから感謝申し上げます。


2025年6月15日日曜日
アダム荒川殉教記念ミサ
世界中のどこかで、おそらく絶え間ないミサと祈りが、殉教者のために神さまの前に捧げられていることでしょう。でも、ときどき思うのです。そのことに果たして意味があるのか、と。
殉教者たちを偲び、追悼ミサを捧げ、祈りの時間を特別に設ける。その行為を否定しているわけではありません。
何十回、何百回と繰り返されてきた祈りとミサが、多少なりとも神さまに届いているのなら、なぜ、20世紀・21世紀がいちばん殉教者を出している、と、言われているのでしょうか。
ロシアとウクライナの戦争は一向に止む気配はなく、イスラエルは傍若無人に他国にミサイルを撃ち込んでいます。最近だけでも、どれだけ多くの信仰者たちがこの戦争で命を落としたことでしょう。
あまりにも不条理です。
だから神はいない!
の、でしょうか? そうではない、と信じています。
私たちが神さまを信仰するのは、どんなに理不尽な日々が続き、この世界は不条理の、漆黒の闇以外の何物でもない。と呻くときでさえ、信仰者たちは、私たちは現状に失望することなく、むしろ希望として、光として全てを神さまに委ねて信じることができるのですから、これほど幸いなことはありません。
あなたは嘘偽りなくそう断言できるのですか? と、問う声があります。
議論の余地はありません。そう告白することこそが「信仰」なのですから。

アダム荒川は、裸にされて横木に縛られ引き回され、三月のまだ寒い時期に朝から晩まで潮風の吹きすさぶ中に吊るされ捨て置かれました。九日間も。
そして、六十日に及ぶ幽閉。しかし、その間も彼は祈り、黙想し、苦難の時を感謝と賛美の日々へと変えていきます。彼の信仰を観て、聴いて、たくさんの人々が感動し、信仰をますます堅くした、と伝えられています。
どんな責め苦にも屈しないアダム荒川でしたが、1614年6月5日早朝、ついに斬首され、その遺体は重い岩にくくりつけられ湾外の海中深くに沈められました。
2025年の今日、私たちはアダム荒川が残した言葉に、覚悟のない私たちの日常を省み、そして誓うのです。「彼の言葉のとおりに私たちも生かして下さい」と。
彼はこう言い遺しました。
「わたしの希望は、石や土でできた教会にあるのではなく、また、時の移り変わりを免れ得ない司祭や、この空の下の何ものでもありません。ただ、神にのみ希望をかけているのです」と。
アダム荒川の、歴史の中のたくさんの殉教者たちの、そして、いまこの時代に死にゆく信仰者たちのたましいに、主の、イエス・キリストの慰めと祝福が溢れんことを祈り願って、今年も殉教記念ミサが幕を閉じました。
2025年4月19日
復活徹夜祭
大江教会で復活徹夜祭が行われました。
いつもの祭儀とは違って、少しばかり複雑ですので、説明については女子パウロ会のホームページから引用させて頂きます。
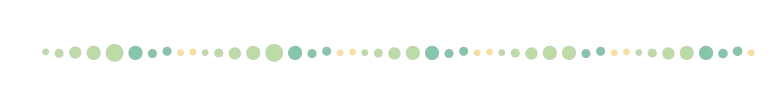
復活徹夜祭の典礼は、4つの部分からなりたっています。
1.光の祭儀:
復活徹夜祭の一つの主役は火であり、光です。

復活されたキリストのシンボルであるローソクの祝福と、光の行列があり、復活賛歌が歌われます。
一同は、聖堂の外に準備された火のそばに集まり、司祭は火を祝福します。その後、この火で司祭は復活ローソクに火をともし、「キリストの光」と歌いながら暗闇の中を進みます。
キリストこそ、「この世を照らす真の光」であり、私たちはキリストの復活によって、闇から救いだされて「光の子」とされたことをあらわします。
光は神の存在のしるし、神の力や恵みをあらわすしるしとして聖書にたびたび登場します。ですから、復活徹夜祭に光の祭儀が行われるのは、キリストの復活のしるしです。
朗読台のそばにあるローソク台に復活ローソクをたて、「声高らかに喜び歌え」と、「復活賛歌」が歌われます。そして、ことばの祭儀へと移っていきます。

2.ことばの祭儀:
救いの歴史をあらわす旧約聖書から7つの朗読、使徒の手紙、福音が朗読され、神の救いのことばと約束に信頼しつつ復活を待ちます。
神がこの世のはじめから、いつも私たちの救いを望んでおられたことを語る救いの歴史を旧約聖書から朗読します。
1)創世記:世界の創造、
2)創世記:アブラハムの犠牲、
3)出エジプト記:イスラエルの民の紅海の渡り、
4)イザヤ書:新しい契約と新しいエルサレム、
5)イザヤ書:救いをもたらす水と神のご意志を果たすことば、
6)バルク書:知恵とその輝き、
7)エゼキエル書:新しい心
この朗読が終ると、新約聖書の中から、「主の復活にあずかる洗礼」の意味をのべる“ローマの信徒への手紙”が朗読されます。その後、「キリストは復活された」と述べる福音書が朗読されますが、今年は“マルコ福音書”が読まれます。そして、洗礼の部に移行していきます。
3.洗礼の典礼:
初代教会からこの日に洗礼が行われてきましたが、洗礼の儀で、洗礼式が行われます。洗礼を受ける人がいないときには、参加者が洗礼の約束と更新をします。
この日のためにずっと準備し、四旬節を励んできた洗礼志願者が、いよいよ教会共同体のメンバーとなる洗礼式です。洗礼は単に個人的な出来事ではなく、教会共同体へ入るわけですから、洗礼の儀では、まず洗礼志願者の紹介があります。
そして、諸聖人の取り次ぎを願う連願(れんがん)、水の祝福、信仰宣言、洗礼、堅信が行われ、信徒一同は洗礼の約束を更新します。
4.感謝の典礼:
新しく洗礼を受けた人たちとともに、感謝の典礼に入ります。ここで、主が死と復活をとおして私たちに準備された食卓に招かれます。この祝いをとおして、教会共同体はキリストの復活にあずかり、新たにされるのです。
カトリック大江教会
住所:〒863-2801 熊本県天草市天草町大江1782電話:0969-42-1111
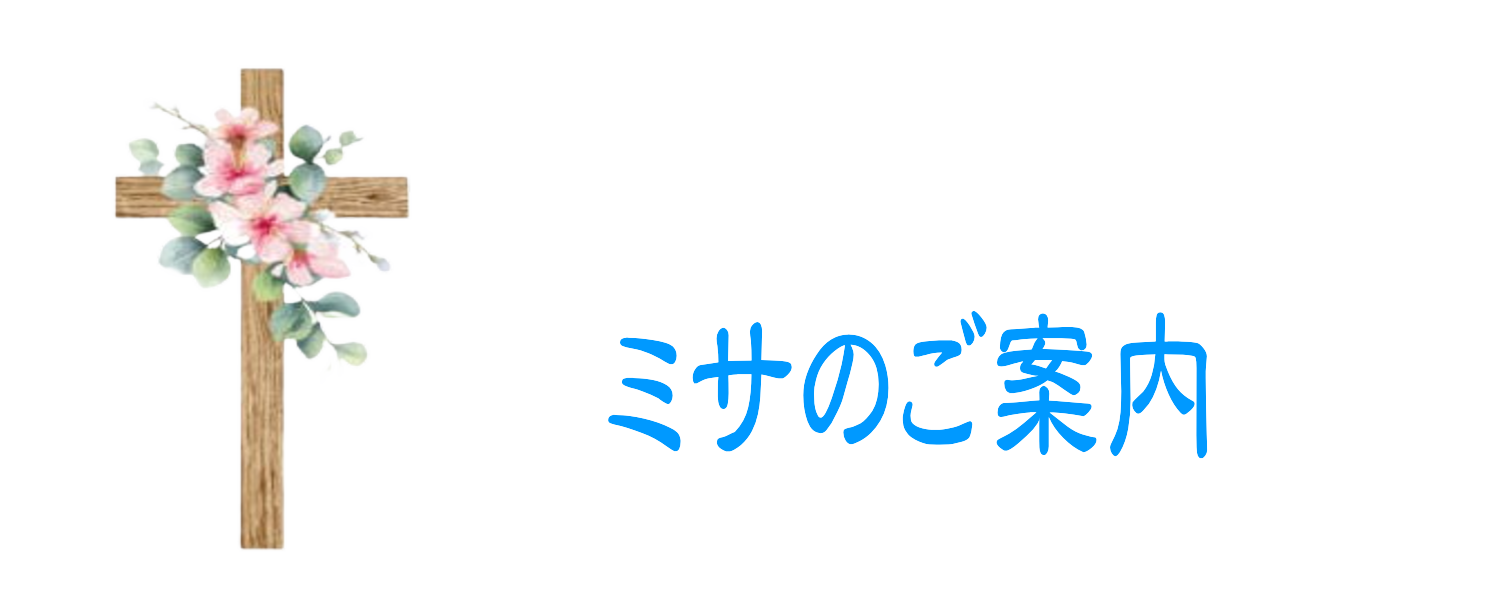
◆主日ミサ
毎週 土曜日 午後6時30分から
◆平日ミサ
井手神父さまの都合で曜日や時間が変更になることがあります。今後のミサ予定を確認してからおいで下さい。
◆今後のミサ予定
○1月12日月曜日 12時から 葬儀ミサ
○1月17日土曜日 夕方6時30分から 年間第2主日 入門講座
○1月24日土曜日 夕方6時30分から 年間第3主日
2026年1月
見よ、新しいことをわたしは行う。
今や、それは芽生えている。
あなたたちはそれを悟らないのか。
わたしは荒れ野に道を敷き
砂漠に大河を流れさせる。
イザヤ書43章19節 新共同訳聖書
2025年12月
主の律法は完全で、魂を生き返らせ
主の定めは真実で、無知な人に知恵を与える。
主の命令はまっすぐで、心に喜びを与え
主の戒めは清らかで、目に光を与える。
主への畏れは清く、いつまでも続き
主の裁きはまことで、ことごとく正しい。
金にまさり、多くの純金にまさって望ましく
蜜よりも、蜂の巣の滴りよりも甘い。
詩編19編8節から11節 新共同訳聖書
2025年11月
そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、 忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。 希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです。
ローマ書5章3節~5節 新共同訳聖書
2025年10月
主は命を絶ち、また命を与え 陰府に下し、また引き上げてくださる。 主は貧しくし、また富ませ 低くし、また高めてくださる。 弱い者を塵の中から立ち上がらせ
貧しい者を芥の中から高く上げ 高貴な者と共に座に着かせ 栄光の座を嗣業としてお与えになる
サムエル記上2章6節から8節 新共同訳聖書
今年も美しいイルミネーションが完成しました。


2025年9月27日土曜日
熊本地区教会合同巡礼ミサ
熊本地区宣教司牧評議会主催の巡礼ミサが、大江教会で捧げられました。


熊本地区所属の15教会から満遍なく信徒さんたちが集い、アベイヤ司教さまの司式のもと、司祭団と信徒200余名が揃いました。これだけの信仰者たちが一堂に会して私たちの主イエス・キリストを賛美するというのは実に荘厳であり、たましいが揺さぶられるような感動に満たされました。
天の御国ではきっと、時間の制限なく、こんな賛美がずっと続いているのだろうな、と想像すると、なんとも夢心地になり、幸せホルモンが溢れてきました。

ミサのひとときは、現実世界の労苦を忘れ、空洞の、乾ききった肉体に、そして霊とたましいにしっかりとちからをいただける時間です。少なくとも私はそうですし、会堂に集われた全ての信徒さんが同じ思いでありますようにと祈りました。
今年は通常聖年にあたりますので、特別な免償を受けるために、たくさんの信徒さんたちが罪の告白とゆるしの秘蹟をうけました。
アベイヤ司教さまの説教は、「希望は欺かない」という内容でした。

その基本は、くしくも殉教者アダム荒川の言葉でした。
朽ち果てるものではなく、また、寿命が尽きるとだれも等しく死んでいく人間にでもなく、ただ神に、イエス・キリストにのみ、望みを託して信仰の旅路を歩いて行く。
そうですね。マタイの福音書24章35節に「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない」。と書いてあります。マルコ13章31節にも同じ事が書いてありますし、イザヤ書40章8節には「草は枯れ、花はしぼむがわたしたちの神の言葉はとこしえに立つ」とあります。
言葉は神であり、神はイエス・キリストです。ただ神に、イエス・キリストにのみ、望みを託して信仰の旅路を歩いて行く巡礼者。それが私たちである。
アダム荒川のように、強く雄々しくあれ。
アベイヤ司教さまはそんな内容で説教を締めくくって下さいました。
またいつか、どこかの教会に集い、旧交をあたためあい、そしてともに主イエス・キリストを賛美する機会を与えて下さるように、信徒皆さんが祈り願った一日でした。
2025年9月8日月曜日
イタリア巡礼団ミサ
イタリアから大司教さま、神父さま方、信徒の皆さん計25名が来島され、ミサが捧げられました。
天草の教会ばかりではなく、熊本の手取教会・島崎教会・帯山教会・健軍教会などからも信徒さんが集まりました。
イタリア語の歌や説教は全く解りませんでしたが、ラテン語の聖歌をともに歌い、日本語の聖歌も数曲あって、こころをひとつにしてイエスさまの救いと贖い、そして愛をかみしめる特別な時間を共有出来たことはなににも代えがたいひとときでした。
イタリアの皆さんも日本の信徒さんたちも、最後はポロポロと涙を流しながら「希望の巡礼者」を歌いました。
世界どこへいっても同じ歌を歌い、同じミサに与ることができる。カトリックに所属していることの幸いを改めて感謝致しました。



2025年8月20日水曜日
川口敏神父さま 特別ミサ
天草市大江出身の川口神父さまが、「聖心のウルスラ宣教女修道会」所属シスター方と来島して下さり、特別ミサを司式して下さいました。
簡潔で解りやすい説教に聞き入りました。
ぶどう園の仕事に従事した労働者たち。朝早くから働いた人たちも、半日働いた人たちも、そして、終業時間ギリギリにぶどう園に入ったひとたちも、皆同じ賃金でした。
当然、早くから働いた人たちは「不公平だ!」と文句を言います。でも、ぶどう園のオーナーは言うのです。「わたしは皆に同じだけ報酬を上げたいのだ」と。
真面目な(?)私は、誰よりも早くに畑に行き、誰よりも遅くまで仕事をするだろうと思います。そして、短気ですから、オーナーに食ってかかり、ほとんど仕事をせずに1日分の賃金をせしめたずるいひとたちに嫌みタラタラ言うだろうな、と思って神父さまの説教を聴いていました。
でも、神さまはそんなクレームなどおかまいなしに仰るのです。「わたしはそうしてやりたいのだ」と。
川口神父さまも、ご自身の経験から「ああ、なんと神さまは太っ腹だろう。神さまの救いと愛はなんと素晴らしいのだろう」としみじみと思い知らされた。そんなお話をして下さいました。
私がオーナーだったら・・・、(悪い意味で)決してこの聖書のようには行動しないだろうと思います。
そうやって、自分を省み、そこから再度、神さま・イエスさまの愛と憐れみを黙想出来た今日の御ミサは、なによりの財産になりました。
ミサには、長崎の「お告げのマリア修道会」から巡礼に来られたシスター方もご一緒でした。大江教会からシスターの姿が消えて以降、久しぶりの光景でした。
あたたかい主の愛に包まれたひととき、川口神父さまとシスター方にこころから感謝申し上げます。


2025年6月15日日曜日
アダム荒川殉教記念ミサ
世界中のどこかで、おそらく絶え間ないミサと祈りが、殉教者のために神さまの前に捧げられていることでしょう。でも、ときどき思うのです。そのことに果たして意味があるのか、と。
殉教者たちを偲び、追悼ミサを捧げ、祈りの時間を特別に設ける。その行為を否定しているわけではありません。
何十回、何百回と繰り返されてきた祈りとミサが、多少なりとも神さまに届いているのなら、なぜ、20世紀・21世紀がいちばん殉教者を出している、と、言われているのでしょうか。
ロシアとウクライナの戦争は一向に止む気配はなく、イスラエルは傍若無人に他国にミサイルを撃ち込んでいます。最近だけでも、どれだけ多くの信仰者たちがこの戦争で命を落としたことでしょう。
あまりにも不条理です。
だから神はいない!
の、でしょうか? そうではない、と信じています。
私たちが神さまを信仰するのは、どんなに理不尽な日々が続き、この世界は不条理の、漆黒の闇以外の何物でもない。と呻くときでさえ、信仰者たちは、私たちは現状に失望することなく、むしろ希望として、光として全てを神さまに委ねて信じることができるのですから、これほど幸いなことはありません。
あなたは嘘偽りなくそう断言できるのですか? と、問う声があります。
議論の余地はありません。そう告白することこそが「信仰」なのですから。

アダム荒川は、裸にされて横木に縛られ引き回され、三月のまだ寒い時期に朝から晩まで潮風の吹きすさぶ中に吊るされ捨て置かれました。九日間も。
そして、六十日に及ぶ幽閉。しかし、その間も彼は祈り、黙想し、苦難の時を感謝と賛美の日々へと変えていきます。彼の信仰を観て、聴いて、たくさんの人々が感動し、信仰をますます堅くした、と伝えられています。
どんな責め苦にも屈しないアダム荒川でしたが、1614年6月5日早朝、ついに斬首され、その遺体は重い岩にくくりつけられ湾外の海中深くに沈められました。
2025年の今日、私たちはアダム荒川が残した言葉に、覚悟のない私たちの日常を省み、そして誓うのです。「彼の言葉のとおりに私たちも生かして下さい」と。
彼はこう言い遺しました。
「わたしの希望は、石や土でできた教会にあるのではなく、また、時の移り変わりを免れ得ない司祭や、この空の下の何ものでもありません。ただ、神にのみ希望をかけているのです」と。
アダム荒川の、歴史の中のたくさんの殉教者たちの、そして、いまこの時代に死にゆく信仰者たちのたましいに、主の、イエス・キリストの慰めと祝福が溢れんことを祈り願って、今年も殉教記念ミサが幕を閉じました。
2025年4月19日
復活徹夜祭
大江教会で復活徹夜祭が行われました。いつもの祭儀とは違って、少しばかり複雑ですので、説明については女子パウロ会のホームページから引用させて頂きます。
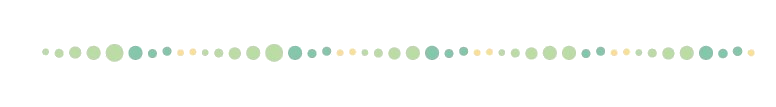
復活徹夜祭の典礼は、4つの部分からなりたっています。
1.光の祭儀:
復活徹夜祭の一つの主役は火であり、光です。

復活されたキリストのシンボルであるローソクの祝福と、光の行列があり、復活賛歌が歌われます。一同は、聖堂の外に準備された火のそばに集まり、司祭は火を祝福します。
その後、この火で司祭は復活ローソクに火をともし、「キリストの光」と歌いながら暗闇の中を進みます。
キリストこそ、「この世を照らす真の光」であり、私たちはキリストの復活によって、闇から救いだされて「光の子」とされたことをあらわします。光は神の存在のしるし、神の力や恵みをあらわすしるしとして聖書にたびたび登場します。ですから、復活徹夜祭に光の祭儀が行われるのは、キリストの復活のしるしです。

2.ことばの祭儀:
救いの歴史をあらわす旧約聖書から7つの朗読、使徒の手紙、福音が朗読され、神の救いのことばと約束に信頼しつつ復活を待ちます。
神がこの世のはじめから、いつも私たちの救いを望んでおられたことを語る救いの歴史を旧約聖書から朗読します。
1)創世記:世界の創造、
2)創世記:アブラハムの犠牲、
3)出エジプト記:イスラエルの民の紅海の渡り、
4)イザヤ書:新しい契約と新しいエルサレム、
5)イザヤ書:救いをもたらす水と神のご意志を果たすことば、
6)バルク書:知恵とその輝き、
7)エゼキエル書:新しい心
この朗読が終ると、新約聖書の中から、「主の復活にあずかる洗礼」の意味をのべる“ローマの信徒への手紙”が朗読されます。その後、「キリストは復活された」と述べる福音書が朗読されますが、今年は“マルコ福音書”が読まれます。そして、洗礼の部に移行していきます。
3.洗礼の典礼:
初代教会からこの日に洗礼が行われてきましたが、洗礼の儀で、洗礼式が行われます。洗礼を受ける人がいないときには、参加者が洗礼の約束と更新をします。
この日のためにずっと準備し、四旬節を励んできた洗礼志願者が、いよいよ教会共同体のメンバーとなる洗礼式です。洗礼は単に個人的な出来事ではなく、教会共同体へ入るわけですから、洗礼の儀では、まず洗礼志願者の紹介があります。
そして、諸聖人の取り次ぎを願う連願(れんがん)、水の祝福、信仰宣言、洗礼、堅信が行われ、信徒一同は洗礼の約束を更新します。
4.感謝の典礼:
新しく洗礼を受けた人たちとともに、感謝の典礼に入ります。ここで、主が死と復活をとおして私たちに準備された食卓に招かれます。この祝いをとおして、教会共同体はキリストの復活にあずかり、新たにされるのです。
