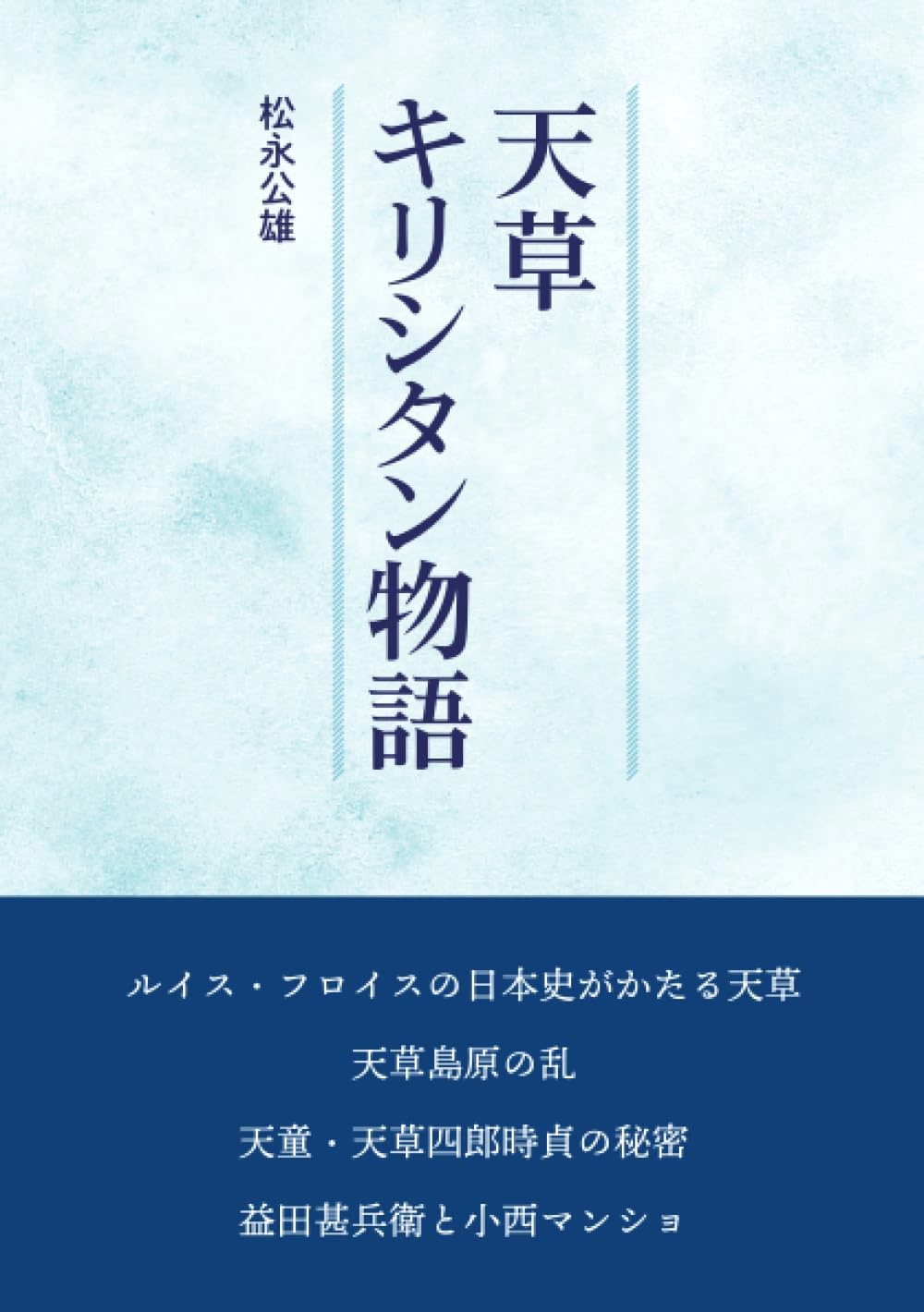教会の動き
2026年1月1日木曜日
新年、あけましておめでとうございます。
神の母聖マリアミサ
元旦は主婦の方々にとってはミサに来にくいですよね。ですから、毎年寂しいミサになるのですが、今日は久しぶりのフィリピン出身の女性信徒さんたちで賑わいました。
若い頃に右も左も分からない日本にやってきて、キリスト教徒ではない日本人男性と結婚し、それでも信仰を捨てることなく、1年に一度であっても教会にやってきイエス様を賛美し、御聖体にあずかる。とても強くたくましいその姿に感動しました。
皆さまの1年に主イエスさまの祝福が豊かに注がれますように。

2025年12月25日木曜日
降誕祭クリスマスミサ
土砂降りに近い雨が降り続くあいにくの天気でしたが、懐かしいおかおも揃って、主の降誕を祝いました。
また、このミサには毎年聖心幼稚園の皆さんも出席して下さいます。子供たちの数も年々減少していますが、彼らが大人になる頃にはきっと世界も平和になっている。そう信じて賛美歌を歌い、神父さまの御言葉を聞き、そして祈り、語り合いました。
子供たちの顔が写真に写り込んでしまいましたので、大方はカットしました。

質素な馬小屋の飾りです。

土台の杉の葉を管理人と相方が採ってきてリースを作りました。

2025年9月27日土曜日
熊本地区教会合同巡礼ミサ(大江教会)
熊本地区宣教司牧評議会主催の巡礼ミサが、大江教会で捧げられました。


熊本地区所属の15教会から満遍なく信徒さんたちが集い、アベイヤ司教さまの司式のもと、司祭団と信徒200余名が揃いました。これだけの信仰者たちが一堂に会して私たちの主イエス・キリストを賛美するというのは実に荘厳であり、たましいが揺さぶられるような感動に満たされました。
天の御国ではきっと、時間の制限なく、こんな賛美がずっと続いているのだろうな、と想像すると、なんとも夢心地になり、幸せホルモンが溢れてきました。

ミサのひとときは、現実世界の労苦を忘れ、空洞の、乾ききった肉体に、そして霊とたましいにしっかりとちからをいただける時間です。少なくとも私はそうですし、会堂に集われた全ての信徒さんが同じ思いでありますようにと祈りました。
今年は通常聖年にあたりますので、特別な免償を受けるために、たくさんの信徒さんたちが罪の告白とゆるしの秘蹟をうけました。
アベイヤ司教さまの説教は、「希望は欺かない」という内容でした。

その基本は、くしくも殉教者アダム荒川の言葉でした。
朽ち果てるものではなく、また、寿命が尽きるとだれも等しく死んでいく人間にでもなく、ただ神に、イエス・キリストにのみ、望みを託して信仰の旅路を歩いて行く。
そうですね。マタイの福音書24章35節に「天地は滅びるが、わたしの言葉は決して滅びない」。と書いてあります。マルコ13章31節にも同じ事が書いてありますし、イザヤ書40章8節には「草は枯れ、花はしぼむがわたしたちの神の言葉はとこしえに立つ」とあります。
言葉は神であり、神はイエス・キリストです。ただ神に、イエス・キリストにのみ、望みを託して信仰の旅路を歩いて行く巡礼者。それが私たちである。
アダム荒川のように、強く雄々しくあれ。
アベイヤ司教さまはそんな内容で説教を締めくくって下さいました。
またいつか、どこかの教会に集い、旧交をあたためあい、そしてともに主イエス・キリストを賛美する機会を与えて下さるように、信徒皆さんが祈り願った一日でした。
2025年9月9日火曜日
イタリア巡礼団とともに
昨日の大江教会に引き続き、イタリア巡礼団の皆さんとともにミサに与りました。
大江教会ではオルガンの奏楽があり、ラテン語と日本語の聖歌を共に歌いましたが、今回はオルガン奏楽もなし。日本語で歌う場面もなし。はじめから終わりまで全てイタリア語でした。
本渡教会の信徒さんたちは借りてきた猫のように静かに、そしておとなしく、お客さん状態でしたが、それでも皆さん終始ニコニコで、とても美しい笑顔でミサを楽しんでおられました。
気軽に世界を旅できる現在でさえ、イタリアまで気軽に出掛けミサに出席し、聖体拝領に与ることはできません。
とても貴重なひとときをイタリアの皆さんに、そしてイエスさまに感謝致しました。




2025年7月28日月曜日
バーバラ・ドロシー・ジェンソンさんの葬儀
教会に集う友人がまたひとり天に召されました。
一週間前まで車椅子に乗って、酸素吸入を受けながらごミサに集い、御聖体も何度も舌の上からこぼれ落ちる。そんな身体で神さまの前に、イエスさまの前に出て赦しを請い、今までの生涯を感謝しておられました。
ドロシーさんの姿を見て、信徒さんたちも、また、弔問にきてくださった他宗教や無神論の方々も胸をたたき、目頭を押さえておられました。
一生懸命に生きるとはなにを意味するのでしょう。
私は思うのです。
神さまの姿は鏡に映った自分自身である、と。
私が近づけば鏡の中の私も近づきます。背を向ければ鏡の中の私も背を向けます。
鏡の中の私の顔が、姿が醜いと思えば、神さまもきっと裁きの神になっておられるのでしょう。
私たちの人生は神さまが、イエスさまが決めたものではありません。自分が選び取って、自分がそういう人生にしてしまったのです。
献花をしながら、病気のせいで全盲になってしまった友人の言葉を思い出していました。
彼は「この病気でどんなに苦しんだかしれない。死のうとさえ思った。毎日『イエスさま助けて下さい』と叫びながら祈り続けた。あるとき解ったんだ。こんな状況でも感謝しないといけないと。そうしたら内側からどんどん力がわいてきた。目は見えるようにならなかったけど、たくさんの導きに恵まれるようになった。もちろん教会にも毎週通えるようになった。いまはつくづく思うよ。この全盲も神さまの、イエスさまの贈り物なんだと」
カナダの大自然のなかで泥だらけ汗まみれになり働いて息子さんを育て、どんな困難に遭っても笑顔を絶やさなかったドロシーさんも、きっと全ての試練を神さまの贈り物だと感謝して教会に集ってこられたのでしょう。
井手神父さまの説教のなかに「死は終わりではありません。私たちキリスト者はその先に希望を見いだしているのです」というお言葉がありました。棺の中のドロシーさんはとても美しい穏やかな笑顔でした。神父さまのお言葉を聴きながら「神父さま、本当にそうでした。こっちにきてそのお言葉の意味がはっきり分かりました。私の人生に、全ての人々に、そしてイエスさまに感謝です」。そう言っておられる。私たちはみなそう確信しお別れを致しました。
ドロシーさんの霊と魂が安らかでありますように。そして、ご遺族の皆さまが慰められ、今まで以上にイエスさまの祝福で満たされますように。祈り続けた一日でした。



2025年7月27日日曜日
2025年度第1回本渡教会委員会
以下のテーマーで話し合われました。
・香部屋担当について
・教会墓地の草刈り清掃について
・女性の会について
・茶話会について
・その他
井手神父さまから
・黙想会について
・昨年1年間の「支え合う教会」の達成度について
・その他
委員の皆さん、お疲れ様でした。
2025年6月29日日曜日
本渡教会信徒総会
前年度活動報告、本年度活動計画。会計報告、監査報告。新執行部選出等が話し合われ、決定しました。
それなりに議論が沸騰しましたが、それは健全な教会であるという証拠です。
信徒全員が、これからも愛し合い、支え合い、助け合い、祈り合う。そんな教会になれますように。
七夕の願いみたいだ? いえぇ~、イエスさまへのお願いです。
2025年6月22日日曜日
井手神父さま歓迎会
ミサの後、手作りの歓迎会を開催しようということで、それぞれが思い思いの手作り料理を持ち寄りました。
その料理のレシピを披露し合う時間がまた大いに盛り上がりました。
ベトナムの女性信徒さんたちが作って下さった郷土料理や、それぞれの家庭料理が並び、壮観な景色になりました。




また、神父さまへの質問コーナーがあり、シンガポールからのゲスト家族による証しがあり、そしてお祈りがありと盛りだくさんな会になりました。
シンガポールの皆さんはプロテスタントの信徒さんご家族でしたが、主イエス・キリストを信じる信仰はカトリックもプロテスタントもない、と改めて確信致しました。



老いも若きも、男性も女性も、また、国籍も関係なく、ともに主の前に集い、皆がひとつ心になって話し、笑い、祈り、食べて、そして飲んでひとときを過ごす。素晴らしい時間でした。
はからずも、この日の福音朗読は、ルカ9章11節から17節。五つのパンと二匹の魚だけでイエスさまが大群衆を養われた箇所でした。男性だけで5000人の群衆。女性や子供たちを含めたらおそらく2万人近くにもなったでしょう。それだけの群衆が食べて満ち足りたのです。
文字通り、食べ物が増えた奇跡、と捉えることもできますし、イエスさまのお言葉は、どんなに小さくても、大群衆の霊と魂を満たしてあまりある、と読むことも出来ます。
いずれにしても、穏やかで、明るくて、希望に満ちた、こころあたたまる交わりのひととき、素敵な歓迎会を与えて下さったイエスさまに皆がひとつになって感謝致しました。
2025年6月15日日曜日
アダム荒川殉教記念ミサ(天草大江教会)
世界中のどこかで、おそらく絶え間ないミサと祈りが、殉教者のために神さまの前に捧げられていることでしょう。でも、ときどき思うのです。そのことに果たして意味があるのか、と。
殉教者たちを偲び、追悼ミサを捧げ、祈りの時間を特別に設ける。その行為を否定しているわけではありません。
何十回、何百回と繰り返されてきた祈りとミサが、多少なりとも神さまに届いているのなら、なぜ、20世紀・21世紀がいちばん殉教者を出している、と、言われているのでしょうか。
ロシアとウクライナの戦争は一向に止む気配はなく、イスラエルは傍若無人に他国にミサイルを撃ち込んでいます。最近だけでも、どれだけ多くの信仰者たちがこの戦争で命を落としたことでしょう。
あまりにも不条理です。
だから神はいない!
の、でしょうか? そうではない、と信じています。
私たちが神さまを信仰するのは、どんなに理不尽な日々が続き、この世界は不条理の、漆黒の闇以外の何物でもない。と呻くときでさえ、信仰者たちは、私たちは現状に失望することなく、むしろ希望として、光として全てを神さまに委ねて信じることができるのですから、これほど幸いなことはありません。
あなたは嘘偽りなくそう断言できるのですか? と、問う声があります。
議論の余地はありません。そう告白することこそが「信仰」なのですから。

アダム荒川は、裸にされて横木に縛られ引き回され、三月のまだ寒い時期に朝から晩まで潮風の吹きすさぶ中に吊るされ捨て置かれました。九日間も。
そして、六十日に及ぶ幽閉。しかし、その間も彼は祈り、黙想し、苦難の時を感謝と賛美の日々へと変えていきます。彼の信仰を観て、聴いて、たくさんの人々が感動し、信仰をますます堅くした、と伝えられています。
どんな責め苦にも屈しないアダム荒川でしたが、1614年6月5日早朝、ついに斬首され、その遺体は重い岩にくくりつけられ湾外の海中深くに沈められました。
2025年の今日、私たちはアダム荒川が残した言葉に、覚悟のない私たちの日常を省み、そして誓うのです。「彼の言葉のとおりに私たちも生かして下さい」と。
彼はこう言い遺しました。
「わたしの希望は、石や土でできた教会にあるのではなく、また、時の移り変わりを免れ得ない司祭や、この空の下の何ものでもありません。ただ、神にのみ希望をかけているのです」と。
アダム荒川の、歴史の中のたくさんの殉教者たちの、そして、いまこの時代に死にゆく信仰者たちのたましいに、主の、イエス・キリストの慰めと祝福が溢れんことを祈り願って、今年も殉教記念ミサが幕を閉じました。
2025年5月18日日曜日
ミサの後、二班に分かれて、教会墓地の草刈りと清掃、教会周囲とルルド周囲の草取り作業を行いました。

キリスト教徒は、お墓やお骨を拝むことはしません。しかし、先に天に召された私たちの愛する家族やご先祖様を思うこころ、偲ぶ心情には、とても強くて、そしてあたたかい優しさを感じます。
教会墓地を奇麗にすることで、信徒さんたちの親睦が深まり、お互いを思いやるこころがより一層強められる、毎回そんな気持ちにさせられる墓地清掃でした。井出神父さま、信徒の皆様、お疲れさまでした。
2025年5月4日日曜日 復活節第3主日
今日は井手神父さまの実質初ミサでした。本渡教会での主日ミサははじめて、という意味ですが、ほとんどの信徒は先月竹内神父さまとご一緒されている井手神父さまのお姿を見て、そのお声を聴いていますので、和やかな雰囲気でミサが始まりました。
しかし、穏やかなそのお声とは打って変わって、とても力強いメッセージにみな圧倒されました。
イエスさまを三度否定したペテロに対して、イエスさまは三度「わたしを愛するか」と問いかけられます。ペテロのこころは当然張り裂けるほどだったでしょう。ペテロは「あなたがご存知です」としか応えられませんでした。
私たちは一生に三度のペテロどころではない、もしかしたら、1時間に三度以上の頻度でイエスさまを否定しているかもしれません。それでも、イエスさまは私たちを赦し、救いへと導いて下さるのです。私たちも、このイエスさまの愛を、イエスさまを知らない人々に、愛を知らない人々に伝える者となりましょう。
こんな内容で語られた説教に、みなこころを打たれました。さらに、日本語が分からない外国籍の信徒さんたちのために、説教の半分は流暢な英語で語られました。
最後に、信徒代表が「歓迎の言葉」を延べ、感動的な、そしてあたたかな雰囲気の中でその日のミサが閉じられました。

と、行けばよかったのですが、管理人の私が書いてきた井手神父さまを歓迎する垂れ幕を披露した瞬間に悲劇は起こりました。
「おぉ~!」という信徒さんたちの声は「えぇぇ~!」という驚きの声に変わり、そして爆笑。え?、なんで? と、意味が解らない管理人の私。ひとりの信徒さんが「でで神父さまになっとるやん」と笑いかけます。そうなんです。私は「井手神父様」と書くべきところを「出手神父様」と書いていたのです。
あぁ~、穴があったら入りたい(T_T)
肝心の井手神父さまは、三度もペテロを赦したイエスさまのように、私のことも笑って赦して下さいました。が、私はきっとこれからもドジをしでかすのでしょう。その度に赦して頂けるのだろうか、と、暗澹たる気持ちになりました。神父さま、そして、信徒の皆さん、申し訳ありませんでした。
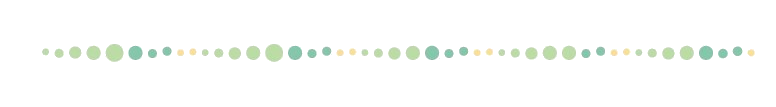
ミサの後、臨時の信徒協議会を開催しました。今後の本渡教会の組織作りについて話し合われましたが、結論は出ず、多くのことを持ち越し、ということになりました。
帰り際、懸案事項であった教会墓地の草刈りと清掃について確認するために、信徒数名で現地の視察に出掛けました。18日の主日ミサのあとに草刈り機などを持ち寄って信徒全員参加で清掃を実施することになりました。雨天の場合は、翌週の25日に日延べになります。皆さまのご協力をお願い致します。
2025年4月27日日曜日 復活節第2主日
竹内神父さまの主司式ミサが最後の日となりました。たった1年でしたがとても名残惜しい、そんな気持ちが溢れてきたミサとなりました。
「『お祝いだけしにきた神父様だった!』と言われそうで心苦しい」という週報の言葉には、読みながら笑ってしまいました。
ぶっきらぼうで余所余所しくて、それでいて熱血漢で、とてもあたたかい。そんな神父さまのことが信徒一同大好きでした。新しい赴任地でもご健康にてご活躍されることをお祈り致します。
後任の井手神父さまが、信徒に代わって竹内神父さまに1年間のお働きに対するお礼の言葉を述べてくださいました。
井手神父さまは、竹内神父さまとは対照的で、ストレートに、そして細やかにご自身の思いを言葉と形にして下さいます。これまた愛に溢れたご性格です。
イエスさまは、私たち信徒に現実を通して日々の出会の妙を学ばせてくださっています。みな、おふたりの神父さまにこころから感謝致しました。
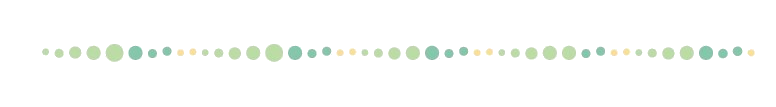
午後2時からは花岡山殉教祭が開催されました。天草の教会からは三人だけの参列となりましたが、とても意義深い式典となりました。
小笠原玄也と彼の妻・みやは、仕えている細川家の熊本移封に伴い、熊本入りとなりました。ときは、幕府のキリシタン詮索が厳しさを増している頃でした。主君忠興・忠利は玄也に転宗の説得を続けます。しかし彼は「ころばざる書きもの」を著し、その意思がないことを表明しました。
その結果、彼は禄を離れることとなり、その暮らしは極貧へと落ちていきます。が、それでも彼ら夫婦の信仰が揺らぐことはありませんでした。
1635年12月、密告によって彼らは長崎奉行へ訴人され、座敷牢に幽閉されることになりました。そして、1636年1月30日、城外高麗門(現在の横手町禅定寺)において処刑され、最期を遂げることとなりました。
小笠原玄也と彼の妻・みや、子供9人、奉公人4人、計15名の殉教の血が流され、彼らの遺体は現在の花岡山に隠し葬られました。


おりしも、フランシスコ教皇さまが帰天され、葬儀ミサが執り行われたばかりでした。
時代や国、場所は違います。不謹慎な言い方ですが、かたや25万人(ネット参列も含めれば数千万人、あるいは数億人)もの参列者で盛大(?)に見送られ、かたや処刑されて血まみれになりながら、その亡骸は捨てるようにしてひっそりと隠し葬られる。
同じイエス・キリストを信仰していながら、この違いはなんなのか、と自問自答し、神さまに祈りました。「あなたはなぜこんな理不尽なことをなさるのですか」と。もちろん声が返るはずもありません。
不思議だったのは、流れ落ちた涙と、「ああ、私は幸せだな」という感覚でした。プロテスタント教会に所属していた時には全く感じたことがなかった思いでした。だからカトリックがいい、プロテスタントはだめだ、と言いたいわけではありません。
ひとにはそれぞれに、神さまから与えられたタラントがあります。そのタラントを使って大きな仕事をする。もちろん、それは大切な務めでしょう。しかし、私にはそうとばかりは思えないのです。
目に見える状況や結果は所詮幻でしかありません。置かれた場所、与えられた時間の中で、いかにイエスさまの愛と福音に繋がっていくか、それだけだ、とこころを新たにした一日でした。
殉教したたましいにも、フランシスコ教皇のたましいにも、そして、いまもなお戦争や災害や不慮の事故、病などで、信仰を堅く保っていたとしても、理不尽にも命をなくしてしまう多くのひとびとと彼らの家族・遺族にも、同じように主イエスの慰めがゆたかに注がれますように。
車を出してくださった信仰の友に感謝いたします。ありがとうございました。
当本渡教会信徒の松永公雄さんが「天草キリシタン物語」を出版されました。Amazonで購入できます。ぜひ手に取ってお読みください。潜伏キリシタンたちの思いが、天草が、そしてイエス・キリストという救い主の存在がより身近に感じられることだと思います。
編著・松永公雄 出版・株式会社PUBFUN
価格・1320円(本体1200円+税)
以下は、巻末に記されている「あとがき」です。
私がルイス・フロイスの「日本史」を読んだのは70才を過ぎてからのことです。こんなことが書いてあるのかと驚きました。この本が世に出たのが1977年。それまで誰ひとりフロイスが書いた日本のキリシタンについての歴史書を知ることがなかった。天草についてこんなことが書いてあるとは大きな驚きでした。これを天草の人に知って頂きたいと言う思いからFacebook
に投稿し始めた。此を読んでくれた友達から是非本にしろと勧められ、ついついその気になって現在に至りました。
フロイスはザビエルの来日の1549年から河内浦のコレジオが出来た1592年ころまでの期間の日本のキリシタンについて書いています。この日本史はまさに歴史書であり、その地で起こった出来事を詳しく述べています。その後、家康の禁教令が1614年発令され、禁教の嵐の後、1637年、天草島原の乱がおこりました。地方での一撲とはいえ江戸時代最大の事件でした。
天草島原の乱については膨大な一次資料が残されており、これらを基にして戸田敏夫氏が書かれた「天草・島原の乱(細川藩資料による)」を読みました。本当によく書かれた歴史書です。その他、天草の歴史家鶴田倉造先生の「天草島原の乱とその前後」、鶴田文史先生の「天草の歴史」に限りなく教えて戴きました。
これらの学術書から学ぶことにより私は「天草キリシタン物語」という論文を書き上げたと言う気持ちでいっぱいです。この4人の先生方に心より感謝致します。今この論文を書き終えて「天草」というところの素晴らしさを噛みしめているところです。
私の論文には四人の先生方の記述を数多く引用させていただきました。しかしただーつだけ説明のつかない人物がいました。それが天童天草四郎時貞です。その大きな空洞をうまく埋めてくれた人物に気がつきました。それが小西マンショです。その他、聖書からの引用が多くなりました。これはキリシタンの物語なのだから仕方のないことです。イエス・キリストの真実の言葉を味わっていただければ幸いです。(松永公雄)